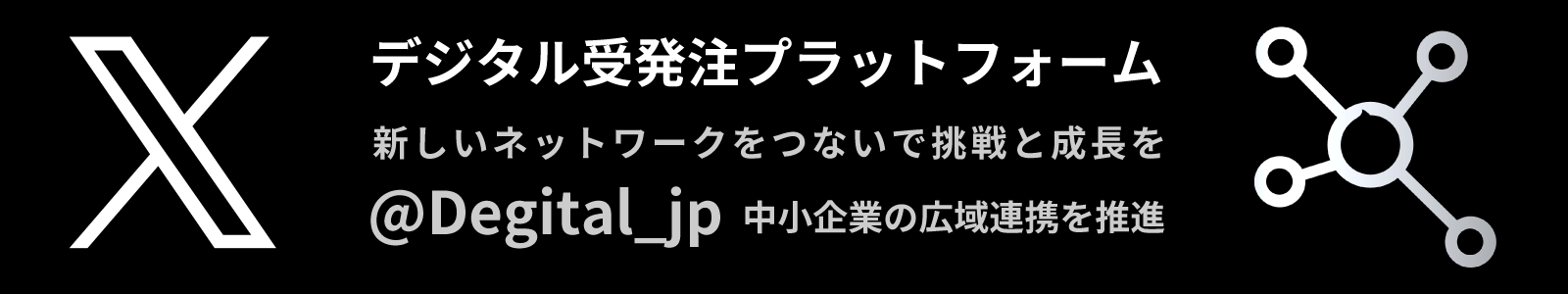- 在庫管理のコストが高すぎる
- 売れ残りのリスクが気になる
- 市場の変化に対応できない
上記の課題を解決する手段として注目を集めているのが、必要な量だけを必要なタイミングで生産する方式「小ロット生産」です。在庫リスクを最小限に抑えながら、市場の変化に柔軟に対応できる生産体制を実現できます。
本記事では、小ロット生産の基本的な概念から、メリット・デメリット、具体的な導入方法まで、製造業の現場で実際に活用できる情報を紹介します。生産方式の改善をお考えの方、製造体制の構築を目指す方は、ぜひ最後までご一読ください。
【今すぐ無料相談】
製造のプロが小ロット生産の可能性を診断します
>>ご相談はこちらから
小ロット生産とは
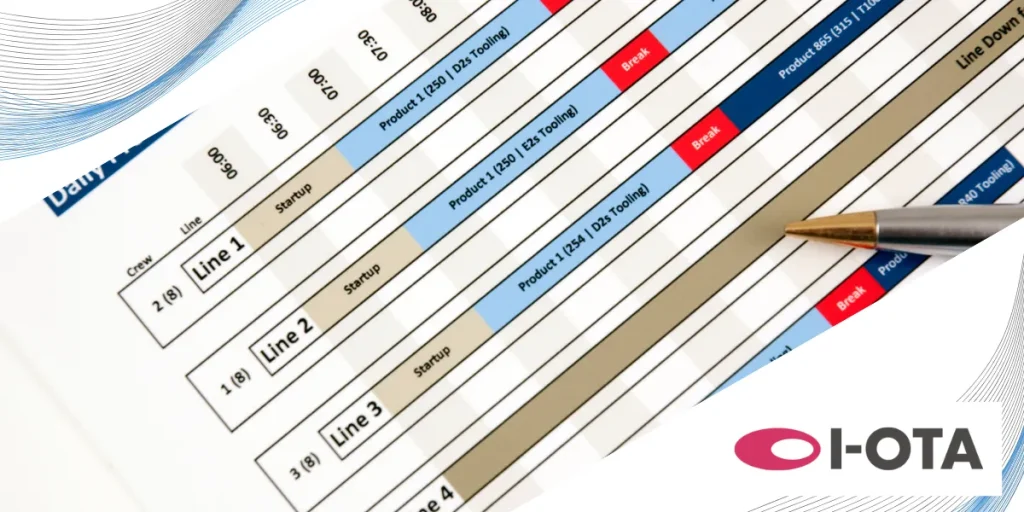
小ロット生産(多品種少量生産)とは、少ないロット数での生産・出荷を行う生産方式です。ここでいう「ロット」とは、製造の生産や出荷における最小単位を指し、例えば100個や1,000個といった具合に設定されます。
昨今のように市場ニーズが多様化し、製品のライフサイクルが短くなっている状況では、過剰在庫は企業経営を圧迫する要因となります。以下を防ぐことで、過剰在庫のリスクを減らせます。
- 保管費用の削減
- 廃棄リスクの低減
- 資金の固定化
また、小ロット生産は新商品の試作や、地域限定商品の製造、季節商品の生産など、さまざまな場面で活用されています。
小ロットと量産の違い
小ロット生産と量産(大ロット生産)では、生産効率とコストの面で違いがあります。
量産は同じ製品を大量に作ることで1個あたりのコストを下げられますが、小ロット生産は段取り替えが頻繁に発生するため、どうしても製品単価が高くなります。
段取り替えとは、機械加工やプレス加工などの生産現場で、ある製品から別の製品を生産するために必要な機械の設定変更や工具交換といった作業のことを指します。
ただ、小ロット生産は、生産数量が少ないことに加え、工場の生産能力の範囲内で柔軟に対応できる方法です。比較的小規模な設備でも顧客に近い場所での生産が実現でき、きめ細かいサービスの提供にもつながります。
小ロット生産と大ロット生産の違い

小ロット生産と大ロット生産では、以下の3つの違いがあります。
- コスト
- 納期
- 生産場所の条件
コスト
小ロット生産は大ロット生産と比較して、製品1個あたりのコストが高くなります。生産ラインの段取り替えや設定変更が頻繁に発生し、作業効率が低下するためです。
また、原材料の調達においても大量購入による割引が適用されないため、材料費も割高になりやすいです。一方で、過剰在庫による保管費用や廃棄損失を避けられることから、トータルでのコスト管理という観点では優位性を持つ場合もあります。
納期
小ロット生産は、一般的に大ロット生産よりも納期も短くなります。生産数量が少ないことで、製造工程全体の所要時間が短縮されるためです。
ただし、工場の生産能力や設備の状況によって、実際の納期は変動します。とはいえ、急な需要変動や追加発注にも柔軟に対応できる点は、市場の変化に素早く適応したい場合にメリットとなります。
生産場所の条件
小ロット生産と大ロット生産では、生産設備や工場の規模も異なります。
小ロット生産は比較的コンパクトな設備で対応可能で、人員も少数で運営できます。そのため、顧客に近い国内での生産が選択しやすく、きめ細かな品質管理や顧客対応が可能です。
一方、大ロット生産では大規模な設備投資と広い工場スペース、多くの作業員を要します。ただし、小ロット生産に特化した工場は大量生産の受注に対応できない場合もあることから、生産規模に応じた適切な委託先の選定を行ってください。
製造で小ロット生産が注目される理由
近年、製造業界で小ロット生産が注目を集めている理由は、マスカスタマイゼーションへの対応です。
マスカスタマイゼーションとは、大量生産と受注生産の2つの生産方式を掛け合わせた新しい生産概念のことです。効率の高い生産を維持しながら、顧客が保有する個別のニーズに応えられます。
特に製品のライフサイクルが短縮化している現代では、市場投入のスピードと柔軟な製品展開が重要です。
小ロット生産は、新製品の市場反応を見るためのテスト販売や、季節限定商品の展開など、リスクを抑えながら市場ニーズを探れる点から解決策として注目されているのです。
小ロット生産に適した製品・分野
小ロット生産は、以下のような製品や分野で特に効果を発揮します。
- オリジナルグッズ(エコバッグ、タンブラーなど)
- ノベルティ商品(缶バッジ、キーホルダーなど)
- ファッション製品(限定コレクション、テスト商品)
- 高級品(カスタマイズ製品、特注品)
- 電子機器(試作品、特殊仕様品)
- 医療機器(オーダーメイド製品)
- 食品・飲料(季節限定品、地域限定品)
いずれの分野にも共通するのは、市場の変化が速く、顧客ニーズの多様化が進んでいる点です。小ロット生産により、このような変化に柔軟に対応できます。
I-OTAでは、大田区の優れた技術力を持つ製造業者が集結した共同事業体として、小ロットからの生産依頼にも柔軟に対応しています。
製品企画から試作品開発、設計、加工まで、ワンストップでサービスを提供できる体制を整えているからです。試作段階からの相談であっても、実際の対話を通じて最適な製品づくりをサポートします。
豊富な現場経験とDX技術を組み合わせた生産体制で、コストダウンも含めたご提案も可能です。製品開発でお悩みの方は、まずはI-OTAにご相談ください。
>>ご相談はこちらから
小ロット生産を選ぶ4つのメリット

小ロット生産を選ぶことで得られる主なメリットは以下の4つです。
- 過剰在庫のリスクを抑えられる
- 試作品の製造がしやすくなる
- ニーズに合わせた生産が可能になる
- 品質管理の精度が向上する
過剰在庫のリスクを抑えられる
小ロット生産のメリットは、在庫リスクの低減です。従来の大量生産方式では、生産効率を優先するあまり必要以上の在庫を抱えてしまい、結果として保管コストの増大や商品の陳腐化するリスクを招いていました。
小ロット生産では、必要な量だけを適切なタイミングで生産できます。在庫の保管費用を最小限に抑えられるだけでなく、商品が売れ残るリスクも軽減できるのです。
試作品の製造がしやすくなる
小ロット生産は、新製品開発における試作段階で特に威力を発揮します。従来の大量生産では、試作品の製造でも一定量以上の生産が必要でしたが、市場投入前の製品テストや品質検証において最小限の数量で製造できます。
製品開発のスピードが向上し、市場の反応を見ながら製品改良を重ねることも検討しやすいです。また、試作コストの削減につながり、より積極的な製品開発も可能になります。
ニーズに合わせた生産が可能になる
小ロット生産の導入により、顧客の細かなニーズへの柔軟な対応も実現できます。市場のトレンドや消費者の嗜好は日々変化しており、従来の大量生産方式では迅速な対応が困難でした。
小ロット生産では、製品仕様の変更や新しい要望への対応を素早く行えます。カスタマイズ製品や季節限定商品の製造において、柔軟性によって市場の変化に応じて生産計画を調整できることで競争優位性を確保できます。
品質管理の精度が向上する
小ロット生産では、各製品に対してより丁寧な品質管理も可能です。大量生産と比較して、一回の生産数量が少ないため、製造工程での品質チェックをより詳細に行えるからです。
不良品の発生を早期に発見し、製造プロセスの改善につなげることもしやすくなります。品質上の問題が発生した場合でも影響を受ける製品数を最小限に抑え、リスク管理の面でも優れています。
小ロット生産を選ぶ3つのデメリット
小ロット生産には、以下3つの主要なデメリットがあります。
- 生産効率が落ちる
- スケジュール管理が難しい
- 従業員の作業の習熟度が上がりにくい
生産効率が落ちる
小ロット生産では、製品の切り替えごとに発生する段取り替え作業により、生産効率が低下します。設備の調整や材料の交換などで機械を停止させる時間が増え、大ロット生産と比べて単位時間あたりの生産量が減少してしまいます。
生産効率の低下に対しては、以下の改善を重ねることで、生産効率の低下を最小限に抑えることが可能です。
- 機械停止中にしかできない作業(内段取り)と、稼働中にできる作業(外段取り)を明確に区分する
- できるだけ多くの作業を外段取りに移行する
- 治具や工具をワンタッチ式に改良する
- 作業手順を標準化し、だれでも素早く確実に段取り替えができるようにする
生産効率だけではなく、先に触れたメリットも踏まえて慎重に検討しなければなりません。
スケジュール管理が難しい
小ロット生産では、多品種の製品を頻繁に切り替えて生産する仕組みによって、スケジュール管理も複雑になりやすいです。急な注文や仕様変更への対応の場合、全体の生産計画に影響を与えやすく、納期遅延のリスクが高まります。
密にコミュニケーションがとれる信頼できる委託先を選定したり、生産管理システムを導入し、リアルタイムで進捗を把握したりする必要があります。余裕を持った生産計画を立て、緊急時の対応手順をあらかじめ決めておくためにも、良好な関係を構築できる委託先を見つけましょう。
従業員の作業の習熟度が上がりにくい
小ロット生産では、同じ製品の生産機会が限られることから、作業者が特定の作業に習熟する機会も少なくなります。結果として、作業効率の向上が遅くなり、品質にもばらつきも生じやすくなります。
- 作業手順の標準化と視覚化を徹底する
- シミュレーション訓練を定期的に行う
- 類似した作業をグループ化し、スキルの転用を促進する
- デジタルツールを活用した作業支援システムを導入する
作業の標準化には、だれでも同じ品質の製品を作れるよう、詳細な手順書やチェックリストの整備が必要です。内部で体制を整える際には、こうした工数がかかることも覚えておきましょう。
小ロット生産を取り入れる方法

小ロット生産を取り入れる方法は、自社で行うか、外部の委託先に依頼するかの2つが挙げられます。いずれにおいても、以下の流れで導入を進めることになるでしょう。
- 現状課題の明確化
- 導入目標の設定
- 社内での実現性の検討
- 実施、または委託先へ相談
これまで小ロット生産の経験がない場合は、委託先の提案やアドバイスを受けながら自社の方向性を決めていくことをおすすめします。専門家の知見は思わぬリスクを未然に防げるだけでなく、品質を保つための手段にもなります。
I-OTAは小ロットからの生産も企画段階から相談可能
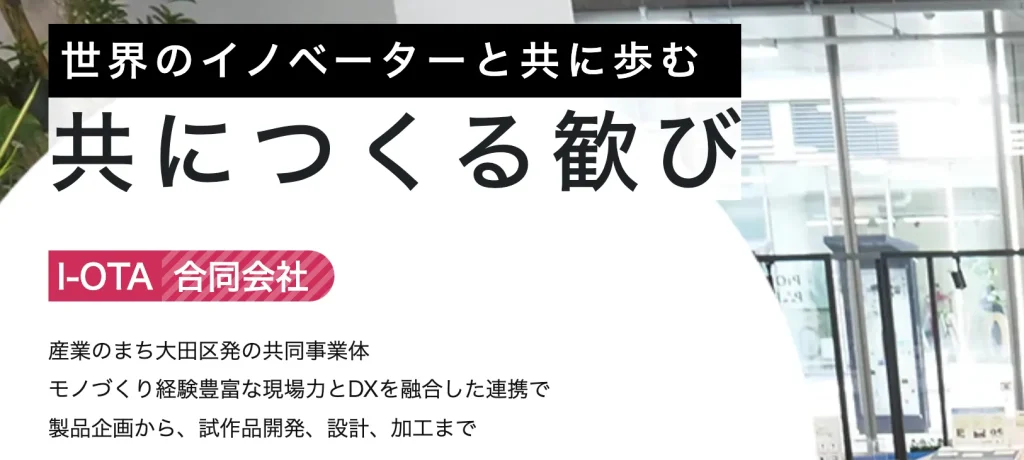
大田区の製造業ネットワークを活用するI-OTAでは、小ロット生産の相談から試作、量産まで一貫してサポートします。
現場力とDXを組み合わせた独自のアプローチにより、従来の町工場の枠を超えた柔軟な生産体制を実現し、お客様のニーズに合わせて、小ロットから量産まで、状況に応じた最適な生産方式を選択できます。
少しでも悩んだり、不安なことがあったりするならまずはお気軽にご相談ください。製品企画や試作開発の段階からでも専門家が、貴社の課題やニーズをヒアリングし、最適な生産方式をご提案いたします。
【今すぐ無料相談】
製造のプロが小ロット生産の可能性を診断します
>>ご相談はこちらから
まとめ
小ロット生産は、在庫リスクの最小化と市場ニーズへの柔軟な対応を実現する生産方式です。過剰在庫による保管コストの削減、試作品製造の容易さ、顧客ニーズへの迅速な対応、そして品質管理の精度向上といったメリットがあります。
小ロット生産の導入を検討する際は、まず自社の課題を明確化し、具体的な数値目標の設定からはじめましょう。その上で、現在の設備や人員体制を評価し、段階的な導入計画を立案してください。
市場環境が急速に変化する現代において、小ロット生産は競争力を高める有効な選択肢となります。自社の状況に合わせた最適な生産方式を選択し、持続可能な製造体制の構築を目指しましょう。