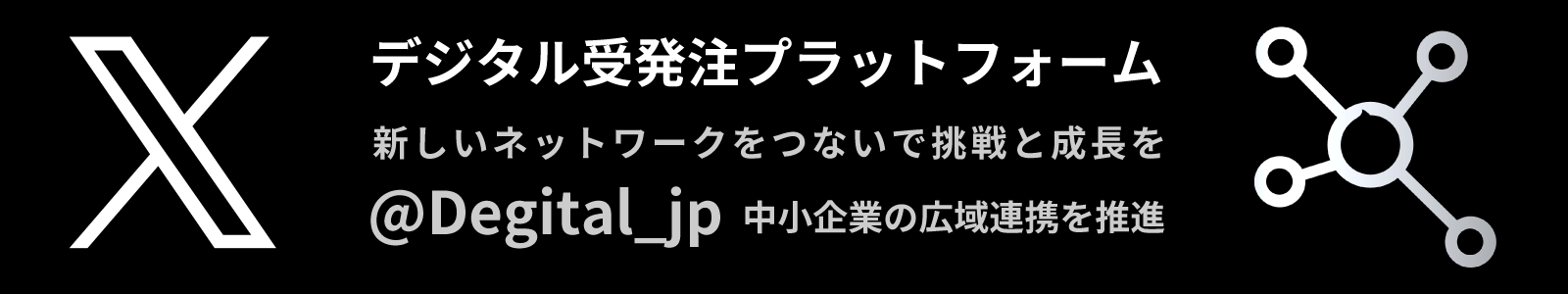皆さんは「デジタルものづくり」という言葉を聞いたことがありますか?最近、製造業の現場でよく耳にするようになったこの言葉。デジタル技術を活用して製造業の設計・生産プロセスを革新し、品質向上・コスト削減・納期短縮を実現する新しいものづくりの形です。
昨今では、従来の「勘と経験」に頼るものづくりから、データと科学的アプローチに基づく新しいものづくりへの転換が進んでいます。CAE(コンピュータ支援エンジニアリング)などの情報システムの導入に加え、AI技術やロボット制御技術を製造プロセスと連携する取り組みが広がっているのです。
この記事では、デジタルものづくりとは何か、どのような技術で支えられているのか、そしてどのようなメリットやデメリットがあるのかを詳しく解説します。製造業の未来を切り開くヒントを見つける参考にしてください。
デジタルものづくりとは?

デジタルものづくりとは、デジタル化によって効率の良い加工や従来難しかった高度な加工を実現する技術体系のことです。これには、CAE(コンピュータ支援エンジニアリング)などの情報システムに加え、AIやロボット制御技術などの最新技術を塑性加工・鋳造・溶接・積層造形などの加工技術と高度に連携します。
従来のものづくりでは、図面を描き、試作品を作り、強度テストを行い、問題があれば設計をやり直す…というプロセスを何度も繰り返し、時間とコストがかかっていました。一方、デジタルものづくりでは、3D-CADで設計したデータをもとに、コンピュータ上でシミュレーションを行い、問題点を事前に発見・修正できます。
これにより、実際に物を作る前の問題を解決できるため、開発期間の短縮やコスト削減につながるのです。
デジタルものづくりを支える5つの中核技術
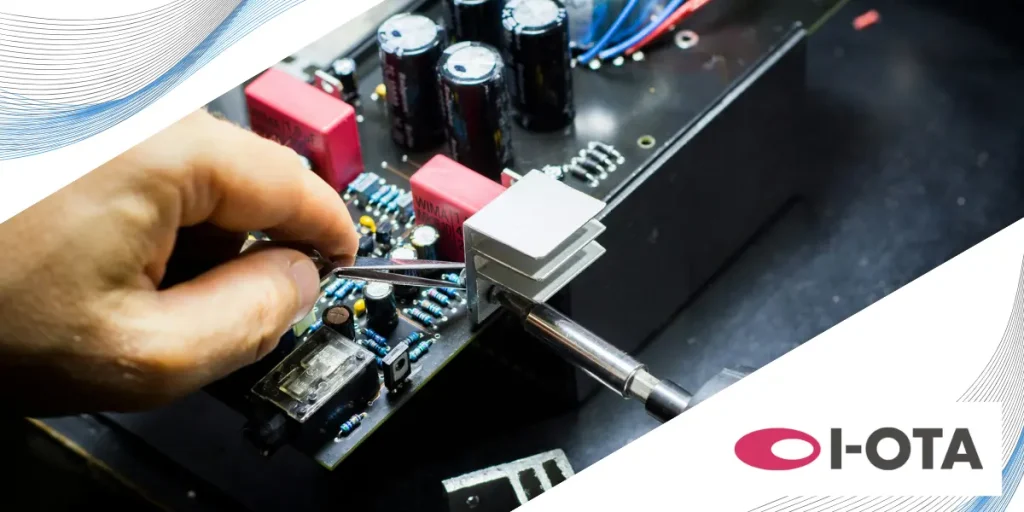
デジタルものづくりを支えるのは、以下に挙げる5つの技術です。
- 3次元CAD/CAMシステム
- シミュレーション技術
- 3Dプリンティング技術
- IoT・センサー技術
- AI・機械学習の活用
3次元CAD/CAMシステム
3次元CAD/CAMシステムは、デジタルものづくりの基盤となる技術です。3次元CAD(Computer Aided Design)は、コンピュータ上で立体的な製品設計を行うツールで、3次元の形状を正確に表現できます。
一方で、CAM(Computer Aided Manufacturing)は、CADで作成したデータから工作機械の制御プログラムを自動生成するシステムです。3次元CAD/CAMシステムの導入により、以下のような効果が得られます。
- 設計ミスの早期発見と修正
- 設計変更の容易さ
- 製造データへの直接変換
- 設計情報の再利用性向上
3次元CAD/CAMシステムは、アイデアを正確なデジタルデータとして表現します。そのデータを製造工程に直接つなげる橋渡し役として、デジタルものづくりの中心的な役割を担っています。
シミュレーション技術
シミュレーション技術は、実際に物を作る前にコンピュータ上で製品の性能や製造プロセスを予測・検証する技術です。CAE(Computer Aided Engineering)とも呼ばれ、強度解析、流体解析、熱解析などさまざまな物理現象をシミュレーションできます。
例えば、目に見えない電磁場や熱の流れをコンピュータで「見える化」できれば、より良い製品設計が可能になります。シミュレーション技術の主なメリットには以下があります。
- 試作回数の削減によるコスト・時間の節約
- 製品の性能予測と最適化
- 製造プロセスの問題点の事前発見
- 複雑な物理現象の可視化と理解
こうしたシミュレーション技術は、実際に物を作る前に「もしも」の世界を探索できます。デジタルものづくりにおける「試行錯誤の効率化」を実現する技術なのです。
3Dプリンティング技術
3Dプリンティング技術は、3次元CADデータをもとに、材料を積層して立体物を造形する技術です。従来の「削り出し」による製造方法とは異なり、複雑な形状も一体成形できる技術です。
従来の削り出しを主とした試作方法と比較して、「造形がスピーディ、低コスト、試作のための工具や冶具(じぐ:加工や組み立ての補助器具)が不要」という特徴があります。
3Dプリンティング技術の主なメリットには以下があります。
- 複雑な内部構造を持つ部品の一体成形
- 少量生産での経済性
- 設計から製造までのリードタイム短縮
- 材料のムダの削減
3Dプリンティング技術は、デジタルデータを直接物理的な製品に変換する「架け橋」として、デジタルものづくりの実現になくてはならない技術となりつつあります。
IoT・センサー技術
IoT(Internet of Things:モノのインターネット)とセンサー技術は、製造現場のあらゆる情報をデジタルデータとして収集・活用する技術です。機械の稼働状況、環境条件、製品の品質データなどをリアルタイムで把握できます。
製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)実現には、IoT技術が必要不可欠です。とはいっても、IoT等のつなげる技術だけでは不十分。今後は、加工する材料の特性、加工プロセスなどのモデル化・データ化、そして利用する技術も必要となってくるでしょう。
主に、IoT・センサー技術は、物理的な製造現場とデジタル世界をつなぐ「神経系統」のような役割を果たします。デジタルものづくりの「感覚器官」として機能しますが、導入や運用にはまだ課題も残っているのです。
AI・機械学習の活用
AI(人工知能)・機械学習技術は、製造業のさまざまな場面で実力を発揮する技術です。大量のデータから法則性や最適解を見つけ出し、人間では気づきにくいパターンを発見できます。
例えば、製造プロセスの複雑な現象をAIの力で解明し、効率の良い加工方法を見つけ出すといった具合です。現場レベルでは、切削条件(速度や送り量など)の最適化にAIを導入し、工具寿命の延長や加工時間の短縮を実現できる見込みがあります。
AI・機械学習は、デジタルものづくりの「頭脳」として機能し、膨大なデータから価値ある知見を引き出します。結果、製造プロセスの継続的な改善を可能にする技術としての位置づけだと考えましょう。
デジタルものづくりがもたらす7つのメリット

デジタルものづくりの導入では、以下のメリットが期待できます。
- 開発期間を短縮できる
- 試作等の製造コストを削減できる
- 品質の向上・安定化を図れる
- 複雑な形状を実現できる
- 少量・多品種生産に対応できる
- 設計の自由度が向上する
- 環境負荷も低減できる
開発期間を短縮できる
デジタルものづくりのメリットの1つが、製品開発期間の短縮です。従来の製品開発では、以下のサイクルを何度も繰り返す必要があり、時間を要していました。
- 設計
- 試作
- 評価
- 改良
デジタルものづくりでは、このような試行錯誤を減らし、開発期間の短縮やコスト削減ができます。例えば、3D-CADで設計し、シミュレーションで問題点を発見・修正したあと、3Dプリンタで試作品を作成するといったことが可能です。
問題があれば設計データを修正して再度プリントするだけです。このように、市場投入までの時間(Time to Market)を削減でき、企業の競争力強化にもつながります。
試作等の製造コストを削減できる
デジタルものづくりは、さまざまな面で製造コストの削減ももたらします。従来は試作や金型製作にコストがかかり、設計変更のたびに作り直す必要がありました。
3Dプリンタを使えば試作段階で試作品を安価に作ることができますし、シミュレーション技術なら「試作レスなシミュレーション」で物理的な試作品を作る回数を減らせます。
単に支出を減らすだけでなく、これまで経済的に実現できなかった製品やサービスも可能にします。コスト削減によって新しい可能性が広がるのです。
品質の向上・安定化を図れる
デジタルものづくりは、製品の品質向上・安定化にも貢献します。人間の感覚や経験に頼る部分を減らし、科学的・定量的なアプローチで品質を管理できるようになるためです。
例えば、伝統的な鋳物製造では、熟練職人の感覚と経験に頼る部分が大きく、品質にもばらつきが生じました。しかし、デジタルものづくりでは、職人の動作をデジタルデータ化し、最適な製造条件を見出すことができます。結果、だれが作っても安定した品質の製品を製造できます。
このように、デジタルものづくりは技術継承にも役立ちます。熟練技術者の知識や経験をデジタルデータとして残し、次世代に引き継ぐことができるのです。
複雑な形状を実現できる
デジタルものづくりの特徴の1つが、従来の製造方法では困難だった複雑な形状の実現です。3D-CADと3Dプリンティング技術の組み合わせにより、これまでの製造上の制約を超えた自由な設計が可能になっています。
例えば、従来の製造方法では作れない、複雑な内部構造を持つ軽量部品を3Dプリンティングで作ることができます。これにより、燃費向上や性能向上が図れるでしょう。
これは、「ものづくりの考え方が変わる」ことを意味しています。製品の機能性や付加価値を高め、これまでにない製品開発を可能にする未来も見えてきたのです。
少量・多品種生産に対応できる
デジタルものづくりは、少量多品種生産に適した製造方法にもつながります。従来の大量生産システムでは、金型製作などの初期投資が大きく、少量生産では採算を取れないケースがしばしばありました。
一方で、デジタル化できれば「必要なタイミングで、必要な量を、必要な場所で製作できる」のです。多様化する顧客ニーズに応え、パーソナライズした製品やサービスを届けるきっかけになるでしょう。
お客様1人ひとりの要望に合わせた製品を、よりお得に製造できる可能性が広がります。これからの時代に求められる、柔軟な生産体制の構築に役立つのです。
設計の自由度が向上する
デジタルものづくりを上手く活用できれば、製品設計の自由度を向上できます。従来は加工技術や金型の制約から設計に制限がありましたが、デジタル技術によりこの制約を緩和できるからです。
「複数部品を一体化して製作したり、既存製品を小型化・軽量化したり」できるようになれば、設計の幅が広がります。「理想的な機能を実現する形状」を優先して設計できるようにもなるでしょう。
このような設計の自由度向上は、製造プロセス自体の革新、ひいては新たな製品開発を可能にするのです。デザイナーやエンジニアの創造力を、最大限に発揮できる環境が整います。
環境負荷も低減できる
デジタルものづくりは、製造プロセスにおける環境負荷の低減にも貢献します。材料のムダや試作による廃棄物を削減できるからです。余分な部分を削り取る従来の方法ではなく、粘土細工のように必要な部分だけを積み上げていくような仕組みだからです。
カーボンニュートラルやSDGs(持続可能な開発目標)などにも目を向け、人・自然に優しいものづくりとなります。「循環型社会」や「5R(Refuse・Reduce・Reuse・Repair・Recycle)」といった環境への配慮は、企業の社会的責任(CSR)や環境規制への対応としても重要です。
環境に配慮したものづくりは、社会的評価の向上にもつながり、企業価値を高める効果も期待できます。
デジタルものづくり導入における4つのデメリット

デジタルものづくりにはメリットがありますが、導入にあたっては注意すべき点もあります。ここでは主な4つのデメリットについて解説します。
- 初期投資コストが高くなる
- 人材の育成が必要となる
- データセキュリティの懸念が残る
- 既存システムとの統合が難しい
初期投資コストが高くなる
デジタルものづくりを導入する際のデメリットが、初期投資コストの高さです。導入には以下のようなコストがかかります。
- 高額な設備・ソフトウェアの導入費用
- 専門人材の採用・育成コスト
- システム統合のための追加投資
- 運用・保守にかかる継続的なコスト
3D-CADシステム、シミュレーションソフトウェア、3Dプリンタなどの設備導入には相当の費用がかかります。中学校の教育現場等に限らず、企業においても同様です。あくまでも例ですが、産業用の金属3Dプリンタは数千万円から1億円以上になることもあります。
このような高額な初期投資を避けるためには、外部委託といった投資しない選択肢も考えなくてはなりません。自社ですべてをそろえるのではなく、必要な機能だけを外部サービスとして利用する方法も検討すべきでしょう。
人材の育成が必要となる
デジタルものづくりとしてデジタル化しても、扱える人材をそろえなければ意味がありません。3D-CAD、シミュレーション、3Dプリンティングなどの技術は一朝一夕に身につかないものです。
人材育成には以下のような課題があります。
- 専門知識・スキルの習得に時間がかかる
- 技術の進化が速く、継続的な学習を要する
- 若手人材の確保が困難になる
- 従来の製造技術と新しいデジタル技術の両方を理解する人材が少ない
例えば、長年旋盤加工に携わってきた熟練技術者であっても、突然3D-CADや3Dプリンタを使いこなせるようになるわけではありません。新しい技術への適応には時間と努力が必要なのも、デメリットだといえるでしょう。
計画的な人材育成プログラムの構築や、外部専門家の活用など、人材面での対策も重要です。
データセキュリティの懸念が残る
デジタルものづくりでは、製品設計データや製造プロセスデータなど、企業の競争力の源泉となる情報をデジタル化します。そのため、データの漏えいやサイバー攻撃のリスクが、新たな懸念事項として浮上するのは必然です。
デジタルデータは容易にコピーでき、一度漏えいすると取り返しがつきません。クラウドサービスやネットワークを介したデータ共有が増えるなか、セキュリティリスクは高まっているといって良いでしょう。
製造システムへのサイバー攻撃が成功すれば、生産ラインが停止することだってあり得ます。データセキュリティの懸念は、専門家と相談しつつ丁寧に対応すべき事柄です。
適切なセキュリティ対策の導入や、社員教育の徹底など、総合的なセキュリティ管理体制の構築が必要になります。
既存システムとの統合が難しい
デジタルものづくりを導入する際、既存の生産システムや業務プロセスとの統合も課題となりやすいです。
長年使用してきた設備や業務フローを一気に変更したらどうでしょうか。当然、反発が起きるでしょう。だからこそ、段階的な移行を計画すべきです。
実際、すべてを最新設備に入れ替えるのは投資対効果から見ても現実的ではありません。古い設備と新しいデジタル技術をどのように連携するか、これが焦点になるのです。
この点は、既存の製造設備や業務プロセスを持つ企業にとっては解決しておきたい課題です。システム間の互換性確保や、段階的な移行計画の策定など、慎重なアプローチが求められます。
デジタルものづくりの導入でお悩みの方は、ぜひI-OTAにご相談ください。大田区のものづくり企業が集まったI-OTAなら、最適な解決策をご提案いたします。
デジタルものづくり導入の3つのステップ

デジタルものづくりに成功するためには、計画的な導入が重要です。ここでは導入の3つの主要ステップについて解説します。
- 現状分析・目標設定
- 適切な技術選定・導入計画
- 段階的実装・効果測定
現状分析・目標設定
デジタルものづくりを導入する第一歩は、自社の現状を正確に分析し、明確な目標を設定することです。何のためにデジタル技術を導入するのか、どのような効果を期待するのかを明確にしましょう。
単に最新技術を導入するだけでなく、自社の製造プロセスの本質を理解し、どこにデジタル技術を適用すべきかを見極めることが重要です。具体的には、以下の流れとなります。
- 現在の製造プロセスの課題や非効率な点の洗い出し
- デジタル化による改善効果が高い工程の特定
- 具体的かつ測定可能な目標の設定(例:開発期間30%短縮、不良率50%削減など)
- 投資対効果(ROI)の試算
闇雲に最新技術を導入するのではなく、自社の課題解決や競争力強化に真に貢献するデジタル化戦略を立てましょう。目標が明確であれば、その後の導入プロセスもスムーズに進みます。
適切な技術選定・導入計画
デジタルものづくり導入の第二ステップは、自社の目標達成に最適な技術を選定し、具体的な導入計画を策定することです。すべての最新技術を一度に導入するのは現実的ではありません。そのため、優先順位をつけた段階的な導入が基本となります。
具体的には以下のようなプロセスを踏みます。
- 目標達成に必要な技術の洗い出し(3D-CAD、シミュレーション、3Dプリンタなど)
- 技術間の連携を考慮した全体システムの設計
- 段階的な導入スケジュールの策定
予算と人材の確保も必要となります。限られた経営資源を活用し、効果を得るための段階といえるでしょう。技術選定では、自社の製造プロセスとの相性や、導入後の運用コスト、将来的な拡張性なども考えることが大切です。
段階的実装・効果測定
デジタルものづくり導入の第三ステップは、計画にもとづいて技術を段階的に実装し、その効果を測定・評価することです。一度に全社的な導入を行うのではなく、特定のプロジェクトや部門でのパイロット導入からはじめ、成功体験を積み重ねていくアプローチが有効です。
例えば、従来の開発方法と比較して開発期間がどれだけ短縮されたか、試作回数がどれだけ減ったかを測定します。成功すれば、その経験と知見をほかのプロジェクトにも展開できます。
このようなアプローチは、リスクを最小化しながら確実に成果を積み上げることも可能です。最終的に、組織全体のデジタル変革を推進するための実践的なプロセスとなるでしょう。
効果測定の結果を次の改善につなげる循環を作ることで、継続的な進化を目指してください。
デジタルものづくりを成功させるための5つのポイント

デジタルものづくりを成功させるためのポイントは、以下の5つです。
- 経営層がコミットメントを行う
- 人材教育へ投資する
- データ活用の基盤を整備する
- 部門の壁を越えた取り組みにする
- 継続的な改善サイクルを構築する
経営層がコミットメントを行う
デジタルものづくりを成功させるための最重要ポイントの1つが、経営層の強いコミットメントです。デジタル技術の導入は単なる設備投資ではありません。企業の事業モデルや組織文化の変革を伴う取り組みであるからこそ、トップダウンのリーダーシップが必要です。
トップダウンのコミットメントはDX(デジタルトランスフォーメーション)等でもよく見かけるはずです。これには、単なる掛け声ではなく、具体的な行動と資源配分を伴うリーダーシップが求められます。
経営層が明確なビジョンを示し、必要な予算や人材を確保することで、組織全体のデジタル変革を推進する原動力となります。社員が安心して新しい取り組みにチャレンジできる環境づくりも重要です。
人材教育へ投資する
デジタルものづくりの成功には、人材の育成も不可欠です。最新のデジタル技術を導入しても、使いこなせる人材がいなければ、期待した効果は得られません。
人材育成のためには、以下のような取り組みが必要です。
- 体系的な教育プログラムの構築
- 外部研修や専門家の活用
- OJT(実務を通じた訓練)の充実
- 継続的なスキルアップの機会提供
人材の育成はコストと見られやすいものですが、実際には企業の持続的な競争力の源泉となるものです。デジタル技術を活用できる人材を育てることは、長期的な企業価値向上につながります。
若手社員の育成だけでなく、ベテラン社員のデジタルスキル習得支援も重要です。世代を超えた知識とスキルの融合が新たな価値を生み出します。
データ活用の基盤を整備する
デジタルものづくりの成功には、データを収集・管理・活用できる基盤整備も欠かせません。デジタル技術の真価は、データを通じた継続的な改善や新たな知見の獲得にあります。データの収集だけでなく、有効活用するための基盤を作らなくては実現できません。
料理の温度や時間を細かく記録・分析し、最適な調理条件を見つけ出すようなものです。製造プロセス全体を通じたデータの流れを設計し、価値創造につなげるために取り組む必要があります。
データ基盤の整備には、センサーやIoTデバイスの導入、データ収集・分析システムの構築、データを活用するための人材育成などが含まれます。総合的に進めることで、データ駆動型のものづくりが実現します。
部門の壁を越えた取り組みにする
デジタルものづくりは、設計・製造・品質管理・営業など、部門の壁を越えた横断的な取り組みも成功に不可欠です。情報の共有と連携によって発揮する相乗効果は、連携強化と全体の効率化にも寄与します。
従来の縦割り組織の壁があるからこそ、成り立っている仕組みもあるかもしれません。しかし、デジタル化によってあえてその壁を取り払い、情報とアイデアの自由な流れを促進することは、イノベーションと効率化を同時に実現するきっかけとなります。
部門横断的なプロジェクトチームの編成や、情報共有プラットフォームの構築など、組織の壁を越えた協働を促進する仕組みづくりが重要です。異なる視点や知識の融合が、新たな価値を生み出します。
継続的な改善サイクルを構築する
デジタルものづくりは、導入して終わりではなく、継続的に改善していくサイクルも必要です。デジタル技術は日進月歩で進化しています。そのため、常に最新の技術動向を取り入れつつ、自社のシステムも進化を図るべきでしょう。
継続的改善のサイクルには、「計画→実行→評価→改善」というPDCAサイクルの考え方が役立ちます。定期的にシステムの効果を測定し、改善点を見つけ、次のアクションにつなげていく仕組みが大切です。
一度の成功に満足せず、常に進化し続ける組織文化を醸成することが、長期的な競争優位性を確保するための取り組みだと位置付けましょう。技術の進化に合わせて、自社のシステムや人材も進化させ続けましょう。
まとめ:デジタルものづくりはI-OTAへご相談ください
デジタルものづくりは、デジタル技術を活用して製造業の設計・生産プロセスを革新し、品質向上・コスト削減・納期短縮を実現する新しいものづくりの形です。3次元CAD/CAMシステム、シミュレーション技術、3Dプリンティング技術、IoT・センサー技術、AI・機械学習などの技術を活用することで、製造業の競争力強化につながります。
しかし、導入にはコストや人材育成、システム統合などの課題も残されている状態です。この課題を乗り越え、デジタルものづくりを成功させるには、専門家のサポートが不可欠です。
I-OTAは大田区の製造業が集まった共同事業体として、デジタルものづくりの導入から運用までトータルでサポートします。お客様の課題に合わせた最適なソリューションをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
デジタルファブリケーションとは何ですか?
デジタルファブリケーションとは、デジタルデータから直接物理的な製品を製造する技術や方法論のことです。主に3Dプリンタやレーザーカッター、CNC工作機械などのデジタル制御された製造装置を用いて、コンピュータ上の3Dモデルや2D図面から直接製品を作り出します。
「ファブ社会」と呼ばれる新しい生産・消費形態の基盤となる技術です。個人のものづくり参加や、オンデマンド生産、地域分散型製造などの可能性を広げています。デジタルファブリケーションは、だれもが自らのアイデアを形にできる環境を提供し、ものづくりの民主化を促進する重要な概念です。
ものづくりとモノづくりの違いは何ですか?
「ものづくり」と「モノづくり」の違いは、主に表記の違いであり、本質的な意味の違いはあまりないとされています。ただし、文脈や使用者によって微妙なニュアンスの違いを生じることがあります。
一般的には、「ものづくり」は日本語の自然な表記として、製造業全般や製品を作る活動を広く指す言葉として使われます。一方、「モノづくり」はカタカナを使うことで現代的なイメージや、先進的・製造活動を強調したい場合に使われることがあります。
どちらの表記を選ぶかは、伝えたいイメージや文脈によって異なりますが、基本的な意味は同じと考えて問題ありません。
製造業におけるデジタル化とは?
製造業におけるデジタル化とは、設計・開発から製造、販売、アフターサービスに至るまでの製造業の全プロセスにデジタル技術を導入し、効率化や高度化を図る取り組みのことです。単にデジタル機器を導入するだけでなく、製造プロセスの本質を理解し、デジタル技術と融合することが重要です。
料理のレシピ開発からメニュー提供、顧客満足度調査までの全プロセスをデジタル化し、効率化・高度化するようなものです。製造業のビジネスモデルや価値創造の方法そのものを変革する取り組みであり、製造業の競争力強化と持続的発展のために不可欠な戦略なのです。
モノのデジタル化とは何ですか?
モノのデジタル化とは、物理的な製品や部品の形状、特性、機能などをデジタルデータとして表現・管理することです。3Dスキャナーやセンサーなどを用いて現実の物体の情報を取得し、コンピュータ上で扱えるデジタルデータに変換します。
モノのデジタル化の主な方法・用途には以下があります。
- 3Dスキャナーによる形状のデジタル化(リバースエンジニアリング、品質検査)
- 産業用CTによる内部構造のデジタル化(非破壊検査、解析)
- センサーによる動作・性能のデジタル化(遠隔監視、予測保全)
- デジタルツインによる製品全体のデジタル表現(シミュレーション、最適化)
デジタル工場とは何ですか?
デジタル工場とは、製造プロセス全体をデジタル技術で統合・最適化した次世代の生産施設のことです。IoT、AI、ビッグデータ、ロボティクスなどの先端技術を活用し、生産効率の向上、品質の安定化、柔軟な生産体制の構築を実現します。
デジタル工場の主な特徴は、以下のとおりです。
- リアルタイムデータ収集と分析(生産状況の可視化)
- 自律的な生産制御(AIによる最適化)
- 柔軟な生産ライン(多品種少量生産への対応)
- 予測保全(設備故障の事前予測と対応)
- デジタルツインによる仮想工場(シミュレーションと最適化)